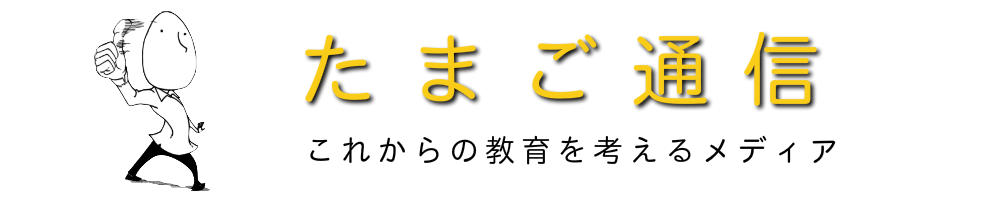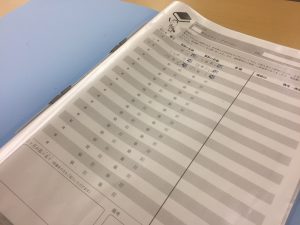「コーチング」で家庭のコミュニケーションをレベルアップ!
小学校高学年から中学生のお子様を持つ保護者の方の中には、
日常の関わりに悩む方も多いのではないでしょうか?
なかなか言うことを聞いてくれない。
思ったようにしてくれない。
ちゃんとやってよ!
そんなことありませんか?
今回は、私達のような教育専門職が活用している「コーチング」という手法をご紹介します。
ぜひ日常のお子様との関わりに活かしてみてくださいね!
2つの「教え方」を知っていますか?

さて、今回はNEXT流という、ご家庭でのお子様との関わりに活かせる教育方法や考えをご紹介するという企画です。
初回の今日は「コーチング」がテーマです。
竹林さん、よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

コーチングというと、少しだけ耳にするという感じの言葉ですが…
その内容がよくわからないという方もいらっしゃいますよね。
改めてわかりやすくご紹介いただけますか?

では、その前に「教える」という行為には2種類あるということをご存知でしょうか?

2種類の「教える」ですか?

はい。そうです。
「教える」という行為には、一方的に知識や技術を与える「ティーチング」と、今回ご紹介する「コーチング」というものがあります。
「ティーチング」といえば、私達が学校教育で習ってきたやり方をイメージするとわかりやすいと思います。

では、「コーチング」というものは、「ティーチング」と具体的にどう違うんでしょうか?

「答えを誰が持っているか」という点に違いがあります。
「ティーチング」は、教える側が答えを握っていると考えます。
そのため、一方的に教える訳です。
一方で、「コーチング」は、学ぶ側が答えを握っていると考えます。

学ぶ側が答えを握っている?
それだと、学ぶ側は全部知っているということになりませんか?
学ぶ側に任せてしまって大丈夫でしょうか?

任せると残念ですがうまくいきません(笑)
勉強に限らずですが、教育の成果は「教える側と学ぶ側の掛け算」だと思っています。
もちろん教える側の教える技術は磨く必要があります。
でも、学ぶ側のやる気がなければ、結局成果は出ませんよね。
教える技術というのは、「ティーチング」、
学ぶ技術というのが「コーチング」とするとわかりやすいのではないでしょうか。

なるほど!
やったほうがいいのはわかるけど、なかなか続かないとか、やる気が出ないとか…
こういうのって子どもも大人も同じですよね。
この勉強に向き合う姿勢や、自分のことを考えたり、自制したり、努力するやり方を教えてあげるというようなことでしょうか?

その説明はとてもわかりやすいですね。
教えてあげるというよりも、一緒に考えてあげるといった感じでしょうか。
考えを巡らせるのも、簡単なことではありませんから、一緒に正しいプロセスで考えてあげ、サポートするという感じです。
人間はとても弱い生き物です。
決めたことを決めたとおりに実行するというのは、なかなか思うようにいかないものです。
24時間テレビで恒例のマラソンでも、必ずトレーナーの方が伴走します。
そのトレーナーがいるから、素人でも走りきれる。
トレーナーがつかずに、本人だけで走らせたら…という結果は誰しも予想できますよね。
コーチングは、なんと“あの会社”もやっている!

私も、今年に入り語学の勉強をしようと決めましたが、全然できていません…。

そうした三日坊主をうまく乗り越えるサービスで話題の会社もありますよね…
あの有名人があっと驚くダイエットに成功し、クルッと一回転するCMで話題の…

あ、もしかして!ライザップですか!(笑)

ライザップも、この「コーチング」と「ティーチング」をバランスよく組み合わせていることで成果を上げているといえます。
技術的なアドバイスと、モチベーション(やる気)を維持したり、高めたりする関わりが武器ですよね。

NEXTでは、そうした取組みはなにかされているんですか?

NEXTでは、スタディ・プランナーというシートを作成しています。
家庭での勉強の内容を確認し、アドバイスをするというものです。
ただ、家で勉強している様子って塾からは確認できないのです。
だから、ぜひご家庭でも勉強の様子を見ていただき、協力してお子様の成長に関わっていければと思っています。
私達も状況に応じアドバイスをさせていただきますので、そのときはお手数ですがご協力いただけますと幸いです。
家でできる!簡単コーチング法!

ご家庭でお子様とのコミュニケーションに悩んでいる保護者の方に、初心者でも実践できる「コーチング」の手法を少し教えていただきたいのですが…

まず、私達の良かれと思っての声掛けがモチベーションを下げていることに注目したいですね。
本人の話を聞かずに、なぜやらないんだ!早く勉強しなさい!量が足りない!…
こうしたことを言っていませんか?
私達もついつい口にしてしまうことはありますが、まずはこちらの想いをあれこれ伝える前に、子どもたちの主張に耳を傾けたいですね。

聞くのもなかなか我慢が必要ですね。

そうです。
まずは最後まで遮らずに話を聞いてあげてください。
なかなか会話が進まないようなら、質問するのも手です。
でも、誘導的に質問したり、「はい」や「いいえ」で答えられる質問(クローズド・クエッション)は会話が続かなくなる原因になるので避けましょう。

どうしても質問すると詰問になってしまいます…
どうしてしないの!とか、ついつい言ってしまいますよね…

どうしてしないの!はもう質問じゃなく、不満をぶつけているだけです(笑)
「どうして?」を「なに?」に変えるといいですよ!
例えば、「宿題を期限までにやらない理由や原因ってなに?」とか…
あとは、「どうすれば宿題やろうって思える?」とか、前向きな質問もいいですね!
ここで冷静になれないと負けですから、ぐっと耐えてくださいね!

言うは易しですね…(笑)

そうですね(笑)
こっちも人間ですから、ムッとすることはありますよ(笑)
でも、ぐっと耐えて!
「馬を水辺につれていくことはできても、馬に水を飲ませることはできない」といいます。
水辺ギリギリまで連れて行くことが私達の仕事です。
水を飲むか飲まないかは本人の課題ですから。
何度も何度も課題と向き合わせてあげることが私達にできることです。

私もやってみます!

そして、質問でさらに具体化してあげるといいですね。
5W1Hとよくいいますけど、なにを?どのくらい?いつ?どこで?誰と?など、
どんどん深掘りして具体的な行動プランに起こしてあげます。
まだ子どもたちの中には、こうして計画を立てることができない子どもたちもいます。
大人だってできない人もいますよね。
だから、サポートして、することを明確にしてあげることが大切です。

確かに、自分で考えるって聞こえがいいですけど、任せたばかりに全然進まないこともありますよね。
具体的に指示されたほうが、やりやすいという人もいると思います。
その人に合わせて、任せたり、管理したりしなければいけませんよね。

その通りですね。
子どもたちは、大人が話す言葉1つ1つを、誰のために言っているか敏感に読み取っているように思います。
大人が思い通りにならないことにストレスを感じているから言っている言葉と、本心から子どもたちのために言っている言葉を区別しているということです。
もちろん、最終的には全て子どもたちのために言っている言葉なんですが、その時々によってその重みづけを読み取っていると思います。

確かに、ああしろ!こうしろ!って私達が言うのって、自分の都合ですよね。
気がつけば、子どもたちの都合が抜け落ちてる。
一方的な命令とも取れます。
それって、大人だって嫌ですよね。

だから、使う言葉にも気をつけたいですよね。
こうした声かけには、「Iメッセージ」という主語が自分の言葉と、「Youメッセージ」という主語が相手の言葉があります。
よく私達は、「〇〇(子どもの名前)!勉強しなさい!」と話してしまいますよね。
これが「Youメッセージ」です。
よく見てみると、「Youメッセージ」は一方的な命令になっています。
一方、「Iメッセージ」というのは、こうです。
「〇〇が勉強せずに携帯ばっかり触っているのって、とっても残念だな。この前約束したのに、守ってくれないの悲しいな。」などと主語が私になっています。
これだと、一方的じゃないですよね。
対話に持ち込むきっかけにもなります。

これだと、より自分のことを思ってくれているように感じられますよね。
大切にされていると感じます。

そうです。結局、家庭でできる「コーチング」ってそこだと思います。
子どものことを認めてあげる。
もっと小さいときは当たり前にしてあげていたはずなのに、私達大人の方が自然とやらなくなっているのではないかと思います。
でも注意してほしいのは、子どもたちの言うことを全部受け入れて!ということではありません。
受け止めることが大事です。
「受け止めてあげる」のと、「受け入れる」のは違う。
必要な努力ができるよう、子どもの考えや思いを受け止めた上で、どうすればいいか一緒に考える。そうした建設的なコミュニケーションが「コーチング」です。

早速やってみたくなりました!
意識してやってみようと思います。
ありがとうございました!

ぜひご家庭での関わりでも活用してみてください。
ありがとうございました!
札幌市北区・東区で学習塾・家庭教師をお探しの方は、当社公式WEBも併せてご覧ください!→http://www.asuxcreate.co.jp
弊社資料請求はこちらから→http://www.asuxcreate.co.jp/next/request.html