中学理科の勉強法
今回はNEXTの提供するサービスや教材の使い方をわかりやすくお届けする「NEXTの使い方」のコーナーをお届けします。
今回は、理科の勉強法についてご紹介します!
それでは早速見ていきましょう!

今回は理科の勉強法ということで、理科チーフの遠田さんをお呼びしました。
よろしくお願いします。

よろしくお願いします。
一問一答が、理科の勉強のスタート

早速ですが、理科の勉強方法をお聞きしていきたいと思います。
まず、理科のテストで点数を取るために必要なことを教えてください!

はい。
理科の得点力は、「基礎知識」と「思考力」と「計算力」に分けられます。
はじめに「基礎知識」をつけることからはじめましょう。

はじめは知識をつけることがスタートということですね。
どのように勉強するのがよいでしょうか?

言葉の定義や意味を覚えることが基本の勉強になりますので、一問一答で演習します。
一日に一気に勉強するよりも、何日も繰り返して勉強するほうが記憶に残ります。
①間違えることを気にせずに、一問一答形式の問題を解く。
②間違えた問題は、解答・解説を確認し、頭の中で音読しながら書いて復習する。
③もう一度とき直す
④解き直してもできなかった問題は繰り返し、できるまでやる。
数回繰り返せば、1ページ30分もかからずにできると思いますので、コツコツ頑張ってほしいです。
計算問題は、頻出事項!問題をたくさん解いて立式力をつける!

まずは語句を知らなければ、その先も問題も解くことができませんからね…。
1つ1つ大事に取り組んでいきたいですね。

一問一答では得意・不得意は出にくいですが、自分でテストのようなつもりで取り組むことは重要です。
一問一答を一通り終えて基礎知識がついたら、計算問題に移ります。

「暗記はできるけど、計算が入るととたんにわからない」という生徒さんもいますよね。
やっぱり計算が入ると難しいのでしょうか?

一見難しそうに見えますが、理科で必要な計算は簡単なものだけです。
ただ、立式で引っかかってしまう場合が多いです。
そのため、解き方のパターンをつかめば意外と簡単に解けてしまいます。

解き方のパターンを覚えることは、数学でも同じでしたね。
勉強方法も、他の教科と同じですか?

さほど違いはありません。
①ワークの問題をひたすら解く
②すぐにわからない問題は答えを見ながら写す
③自分でできなかった問題を中心に全範囲を見直し、やり方を覚える
④全範囲をもう一度解き、できない問題にチェック
⑤チェックをつけた問題にだけ取り組む
⑥すぐに答えが思い浮かぶまで繰り返す
この要領で勉強しましょう!
作図は高配点!ワークで力をつけよう!

できる問題がどんどん増えていくのが目に見えると、嬉しいですよね。
基本の勉強は、ワーク。そしてそれを繰り返すことということですね。
ところで、理科では作図もありますよね。
どのように勉強すればよいでしょうか。

はい。
作図の問題もパターンは限られています。
こちらもワークを繰り返し解いてパターンを覚えてしまいましょう。
なぜそうなるのか気になったら、理解できるまでトレーナーに確認してください!
簡単な問題が多い割に、テストでは配点が高得点のことが多いので、作図は落とせません!

作図は簡単な割に配点が高いんですね!
それは、絶対に取らなくてはいけませんね。
理科の入試は、近年難化傾向にあると聞きますが、入試の対策はありますか?
入試・道コンでは、戦略的に点を取ろう!

そうですね。
まずは、大問1の小問集合を確実に得点したいです。
基本的に計算問題がなく、一問一答で出題されるので、難易度が低いです。

難易度が低いということは、差がつきにくいということですね。

逆にここで落としたら点数は伸びません。
大問1以外の各大問は、実験形式の出題です。
実験の説明で文字が多いですが、ヒントが多いということでもあります
しっかりと読むことが大切です。

理科の問題では、図や表がたくさんでてきてややこしいですよね。

問題文を読むのに時間がかかってしまうので、理科は時間との勝負です!
データの中には、いまの問題で使うものや、次の問題で使うもの、中には使わないものも混ざっています。
自分に必要な情報とそうでない情報を見分けて、式を立てる練習が必要です。

時間との勝負ですか…。

理科が苦手な人には、大きく分けてパターンが3つあります。
①そもそも語句を知らないこと。これは勉強不足ですので、インプットからやり直しです。
②情報収集不足。問題文の読み方が身についていないので、「何を問われているか」、「何を答えるか」を意識して問題を解いてください。
③ 立式できないこと。これは解法のパターンを理解できていないということです。たくさんの実験問題に触れ、解法を体で覚えましょう。

理科の勉強は、一問一答で知識を蓄えて、あとは実験問題をたくさん解くということがわかりました。

理解した実験の数がそのまま点数に反映されます!
あやふやなところは、一人で無理せず、私達に聞いてください。

まずは、簡単な一問一答から手をつけていきたいですね。
本日もどうもありがとうございました。

こちらこそありがとうございました。
札幌市北区・東区で学習塾・家庭教師をお探しの方は、当社公式WEBも併せてご覧ください!→http://www.asuxcreate.co.jp
弊社資料請求はこちらから→http://www.asuxcreate.co.jp/contact.html
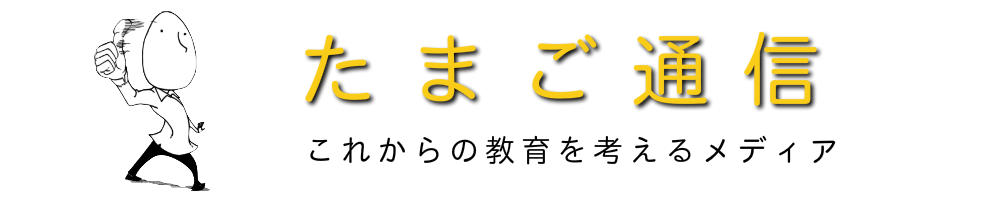
-300x169.jpg)
